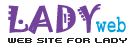肥満と体質と遺伝子
肥満の原因として遺伝子によるものが30%、生活環境によるものが70%程度であると言われ、この遺伝子が左右する肥満の要因のひとつに、褐色脂肪細胞の働きの違いがあるようです。
白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞
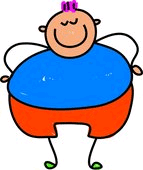
体内の脂肪細胞には、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類があり、白色脂肪は体内に入ってきたエネルギーを中性脂肪として蓄えます。よく「脂肪」と言う言葉で使われてるのはこの白色脂肪細胞のことです。
この白色脂肪細胞は、下腹部や太もも・背中・二の腕や内臓の回りなどに多く存在し、体重がそれほど多くなくても、下腹部やお尻、太ももなどの太さが目立つ人は、その部分に白色脂肪細胞が多いのでしょう。
褐色脂肪細胞は、蓄えることの出来る脂肪が白色脂肪細胞よりも少なく、首の周りや脇の下・肩甲骨の周り・心臓・腎臓の周りなどについて、体内に蓄積された余分なカロリーを熱にかえて放出させる働きのある細胞です。
人間は体温を一定に保つことの出来る変温動物で、寒いと感じると蓄えた脂肪を燃焼し、その熱で体温を上げ維持します。これもエネルギーをたくさん消費する基礎代謝のひとつです。
白色脂肪細胞から燃料となる中性脂肪を受け取って燃やしてくれるわけですから、この褐色脂肪細胞がガンガン働く人は肥満になりにくいわけです。
でも、褐色脂肪細胞は成長期に入ると少しずつ減っていくらしく、年を取ると身体に脂肪がつきやすくなるのは、この褐色脂肪細胞が減ってくることも要因にあるようです。
日本人は太りやすい体質?
もともと日本人は脂肪を蓄えやすい。
欧米人ほど食の豊かな国ではないので、少ない食料で生きてく体になってるわけでしょうね。
そんな体質なのに欧米人並みの食生活になってる今は、肥満が増えるのもわかるような気がします。
肥満遺伝子
肥満と大いに関係する「基礎代謝」。
肥満に関する研究により、基礎代謝で使われるエネルギー量は「肥満遺伝子」と呼ばれる遺伝子によってある程度左右されることが分かってきてるらしいです。
50を超えるタイプの肥満遺伝子があることが明らかにされていますが、このうち日本人に関係する主な肥満遺伝子は、β3アドレナリン受容体(β3AR)・脱共役たんぱく質1(UCP1)・β2アドレナリン受容体(β2AR)で、それぞれ約34%・約25%・約16%の人がこの肥満遺伝子を持っているようです。
- β3アドレナリン受容体(β3AR)
-
りんご型と呼ばれるのがこのタイプ。
約34%の日本人が該当しているようです。
このりんご型は、1日当たりの基礎代謝量が非保有者より200キロカロリーほど少なく、お腹回りが「ぽっこり」と出ているのが特徴です。
- 脱共役たんぱく質1(UCP1)
-
洋なし型と呼ばれるのがタイプ。
約25%の日本人が該当しているようです。
この洋なし型は、1日当たりの基礎代謝量が非保有者より80~100キロカロリーほど少く、腰や太ももといった下半身に皮下脂肪がつきやすいのが特徴です。
- β2アドレナリン受容体(β2AR)
-
バナナ型と呼ばれるのがタイプ。
約16%の日本人が該当しているようです。
このバナナ型は、1日当たりの基礎代謝量が非保有者より200キロカロリーほど高く、ほっそりとしていて太りにくいのが特徴で、筋肉が付きにくい上に落ちやすく太るのが困難な体質です。「逆肥満遺伝子」と呼ぶ方が適切でしょう。